偏差値50前後から逆転合格を目指すあなたへ。
「何から始めたらいいの?」「どれくらいのペースで進めれば間に合うの?」
そんな悩みを解決するために、この記事では【大学受験の勉強計画】の立て方を5ステップで解説します。
✅ 1年間の学習スケジュール
✅ 月別・科目別の戦略プラン
✅ 1日の勉強ルーティンや使用教材例
すべて掲載。大学受験スケジュールテンプレを探している方にとっても、すぐに実践できる構成になっています。
大学受験に向けた勉強計画の立て方を解説!
いつ、何を、どのペースで進めるべきか?
1年間の学習スケジュール・科目別戦略・1日の勉強計画まで詳しく解説!
共通テスト&二次試験対策にも対応!
大学受験には計画が非常に重要
大学受験は、科目が多く、それぞれのボリュームも非常に大きいため、計画的に学習を進めることが必須です。計画を立てずに勉強を始めてしまうと、気づいたときには手遅れになってしまうこともあります。大学受験で合格を勝ち取るには、正しい勉強スケジュールがカギです。この記事では、月別・科目別に最適な学習戦略を解説します。
まず大切なのは、「いつ」「何を」「どれくらいのペースで」学習するのかを把握することです。学習計画を立てることで、長い受験勉強の過程でのモチベーション維持にもつながります。受験はマラソンのようなもので、最初の勢いだけではなく、継続して学習することが求められます。
【年間計画】大学受験を5ステップで攻略する戦略とは?
まずは、受験勉強を 「5つの期間」 に分けて考えます。
① 春〜夏休み前:合格の土台をつくる『基礎固め期』
この期間は 基礎を徹底的に固める ことが最優先です。特に国語・数学・英語の3科目は、短期間で成果が出にくいため、早い段階で基礎を盤石にしておくことが重要です。
例えば、
- 国語:古文単語・漢文法の徹底
- 英語:英単語・熟語・文法の定着
- 数学:教科書レベルの問題の理解
この期間は焦らずに基礎を積み重ね、秋以降に成果が出るよう準備しましょう。
この時期の基礎固めに最適な受験テキスト(参考書や問題集)を別記事にておすすめしています!
そちらも是非お読みください。
② 夏休み中(演習開始&弱点補強)
基礎がまだ不十分な場合は、夏休み中に急いで補強を行います。すでに基礎が定着している場合は、入試問題の基礎レベルの演習に取り組みましょう。
夏休みは受験の天王山といわれるように、非常に重要な時期となります。この時期に今までと同じような夏休みを過ごしてしまうと、その後の受験に大きく響き、受験校の選択肢が限られてきます。
「自分は受験生なんだ!」「目標に向かって突き進むんだ!」と強い意志と覚悟を持ってこの時期を過ごすようにしてください。
この時期のポイント:
- 1日 8〜10時間 の学習時間を確保
- 勉強をする環境を整える
- 朝〜夜のタイムスケジュールを細かく設定
- インプットとアウトプットをバランスよく行う
勉強時間を確保することはもちろんなのですが、特に意識すべきことは、勉強する環境を整えることです。どういうことかというと、長時間勉強しなければならないので、誘惑物が近くにあるとどうしてもそちらに流れてしまい、サボってしまいがちです。
やらなきゃいけないとわかっていても、甘さを捨てられない自分自身を攻める人もいます。ですが、甘えてしまうこと、割とそれ自体は自然なことなので、自分を否定する必要はありません。
しっかりと受験勉強を長時間こなせる人は、”甘えてしまうその環境”を自ら制限をかけ、甘えられない仕組みを作っています。
家ではどうしても甘えてしまうため、塾の自習室に行ったり、カフェに行ったりと、甘えてしまう環境を避けています。そういった、勉強する環境と休む環境にメリハリをつけて過ごしていく必要があるかと思います。
勉強する環境については以下の記事でも紹介していますので、是非こちらもお読みください。
③ 夏休み後〜冬休み前(弱点補強&試験形式に慣れる)
この期間は 共通テスト対策 を本格的に進め、試験形式に慣れることが重要です。
苦手単元については、その単元に絞り、基礎から必要であればそこまで戻り徹底的に復習を行う必要があります。なんとなくの理解で進めてしまうと、実際の過去問対策を行う際に、対応できなくなります。入試問題は基礎がしっかりと定着していないと解けません。そういう風に本当によくできています。そのためには、やはり「基礎力」が非常に重要で、不十分の単元は、教科書や学校ワークまでしっかりと戻って学習し直してください。そこまで戻るのが不安・・・間に合うかな、と不安になる気持ちも非常によくわかりますが、中途半端に戻るより、しっかりと戻ることが結果的に近道です!
入試基礎問題に触れる(対策する)際、意識すべき重要なことがあります。それは、
答えが何であるかより、答えにもっていくまでの過程が大事
ということです。
入試基礎レベルの問題から、一問一答レベルではなく、1つの問題を複数の知識をもって解かなければなりません。ですから、「なぜその答えになるのか?」を常に意識して、その問題を向き合ってみてください。その問題を解く上で、
- 必要な知識はどんな知識だったか?
- その知識はどのテキストに載っていたか?
- どんな勉強をしていればその問題が解けたのか?
これらを意識して、一つの問題を丁寧に扱って、知識をつけていくことで、入試問題の基礎に触れていきましょう!
- 各科目の解答プロセスを理解し、演習を繰り返す
- 理科・社会 はこの時期に仕上げる(教科書や学校ワークを活用)
- アウトプット中心 の学習(模試のやり直し、過去問演習)
④ 冬休み:共通テスト本番直前、過去問で仕上げる時期
共通テストを受験する場合、 過去問を最低10年分 解き、解答のプロセスをしっかり意識して学習を進めます。過去問の扱い方は、上記の③でも触れたように、答えまでのプロセスを大切にしてください。
- 重要なのは「答え」ではなく、「解答までの過程」
- どの知識を使い、どう考えれば解けるのかを理解する
- 時間配分の調整もこの時期に行う
⑤ 二次試験前(志望校別対策)
二次試験の問題傾向を徹底的に分析し、 志望校対策 を行います。国公立大志望であれば二次試験、私立志望であれば独自試験問題。その大学の入試問題を徹底的に分析し、どういった分野が出題されているか、必要な知識は何か、時間配分は大丈夫か、など本番をイメージしながら対策しましょう。
- 過去問を繰り返し解き、解法パターンを把握する
- 時間配分や試験戦略を固める
- 記述式の解答を意識し、添削を受けることも有効
計画通りにいかないことが当たり前
計画を立てても、 100%その通りに進むことはほぼありません。 しかし、それは決して「失敗」ではありません。
大事なのは、「計画を立てる → 実行する → 修正する」を繰り返すことです。この 修正力 を鍛えることで、柔軟に対応できる受験勉強が可能になります。
また、計画にはある程度の余裕を持たせることが大切です。細かく計画を立てつつも、スケジュールには余白を作り、適度に休憩時間を入れることで、持続可能な学習習慣を身につけましょう。
【1日を最大化】受験生のための時間の使い方ガイド
学校のある日とない日で計画を立てる
【平日】
平日に関しては、基本的に学校があるので、それを考慮した計画を立てる必要があります。
また、意識してほしいこととして、『学校のあっている時間帯は、自分自身に本当に必要な勉強は、できない』ということです。言い換えれば、みんなと同じ勉強しかできないということです。
つまり、学校が始まるまでの時間や終わってからの時間の使い方が非常に重要となってきます。
- 朝は単語などの記憶をルーティン(習慣)にし、学校終了後からは自分の計画したことを行う
- 夕方以降の学習時間を確保し、得意科目・苦手科目をバランスよく勉強する
【休日】
休日に関しては、まず、平日と同様の生活リズムで生活をする、ということが重要となります。
『朝は学校がある日と同じ時間に起き、夕方まで勉強し、夜は寝る』
この生活リズムを崩さずに、計画を立てましょう。
- 平日と同じリズムで生活することが重要
- 朝から計画的に学習し、自分のペースで進める
具体的な1日のスケジュール例(学校のある日)
- 07:00〜07:30(家):英単語(システム英単語)
- 17:00〜18:00(家or塾):数学の演習(白チャートの二次関数)
- 19:00〜20:00(家or塾):英語文法(ビンテージの仮定法)
- 21:00〜22:00(家):暗記科目(古文単語・社会)
無理のないスケジュールを立て、「1日5時間やる!」ではなく、「30分×5回やる!」 の意識を持つことが大切です。
休日の勉強時間を最大限に活かすには?
「学校がない日はどう勉強すればいい?」という方は、
こちらのテンプレート付き記事もおすすめです⇩
受験計画の極意|“修正できる人”が最後に勝つ
受験勉強は 計画がカギ! いつ・何を・どのペースで進めるかを明確にすることで、着実に学習を進められます。
また、計画通りに進まなくても焦る必要はありません。修正しながら進める柔軟性 を持つことが合格への近道です。無理なく持続できる計画を立て、1冊の問題集を完璧に仕上げる意識を持ちましょう。
受験サポートのご案内
「計画の立て方がわからない!」という方は、 受験戦略のサポート も行っています。
気合いはあるけど、自分だけではどうしても不安だし、だれかにサポートしてもらいながら、「これが正解!」とある程度確信をもって取り組んでいきたい、と感じている方は是非、以下から受講を検討されてみてください!やる気のある方であれがどんな方でも、全力でサポートいたします!一緒に受験と戦っていきましょう!


🔗受験のご相談や学習計画サポートを行います 学校や塾の宿題でわからないところもしっかり解説します!
受験相談や勉強の質問対応など、さまざまなニーズにお応えいたします。

BASEショップ
進路相談・学習法のアドバイス、保護者向けの受験サポート相談、学校の宿題・塾の問題など、分からない問題の解説まで対応、学習計画の提案など、ご要望に応じて対応いたします。
⇩また、その他にも受験に関する記事も御座いますので、是非一度お読みください。お役に立てればと思っております。
- 受験に関する記事をもっと読む →[受験コンシェルジュ -親子で合格へ-|note]
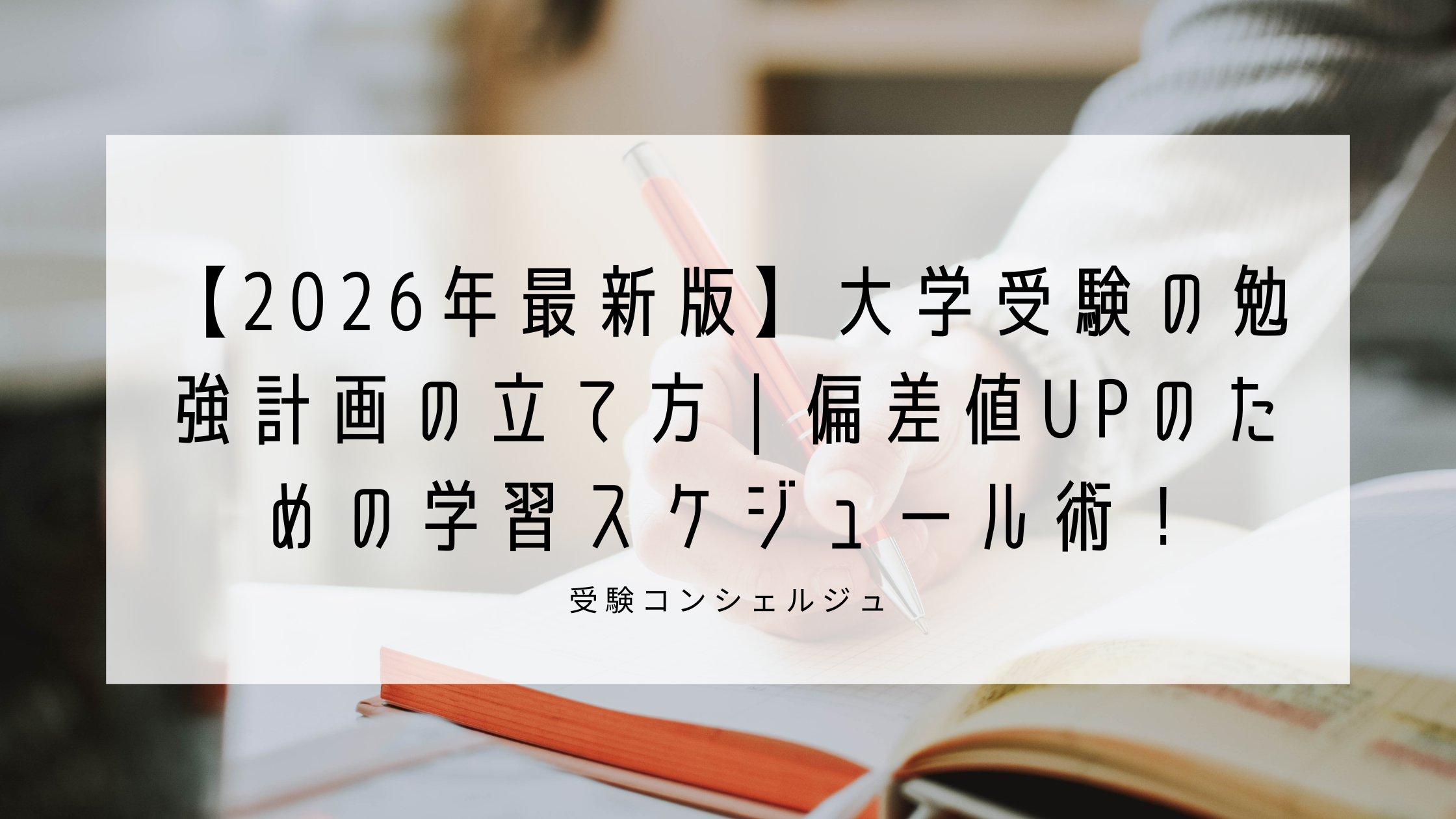

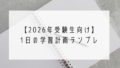
コメント